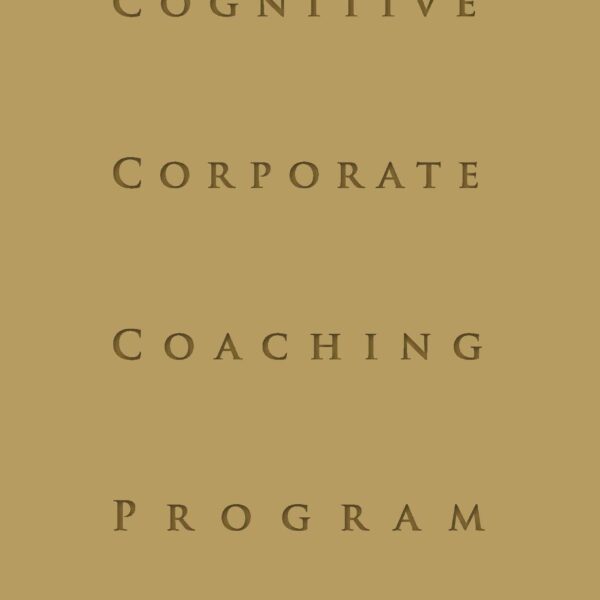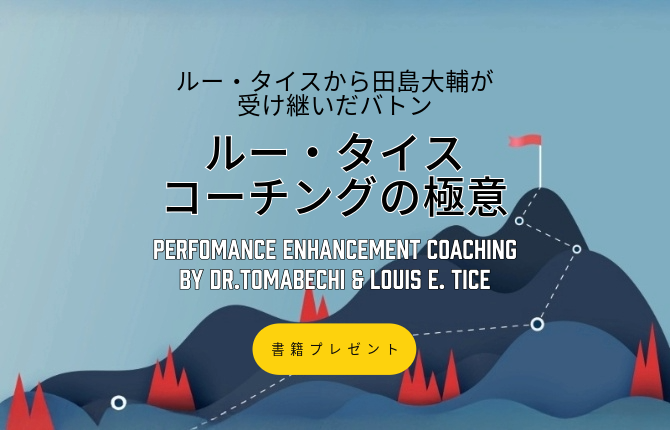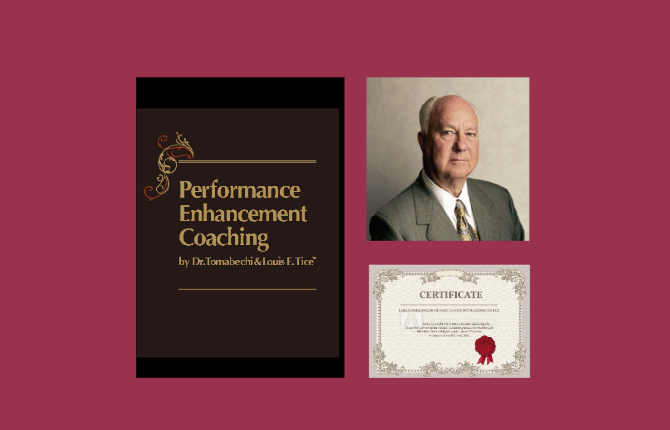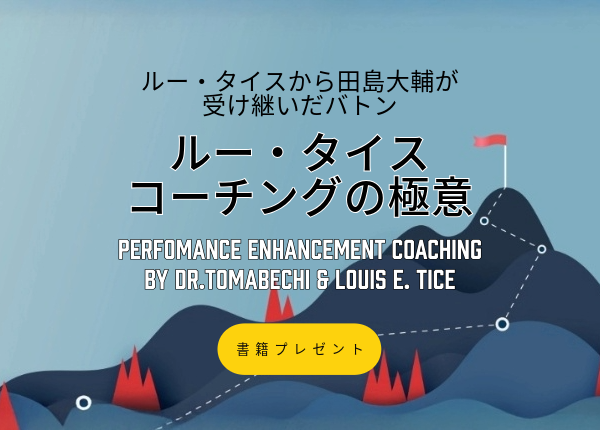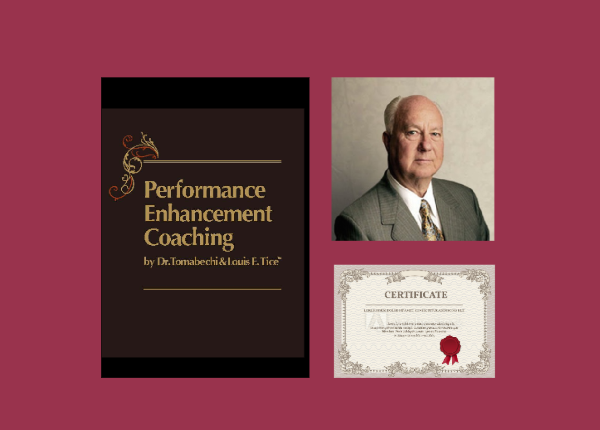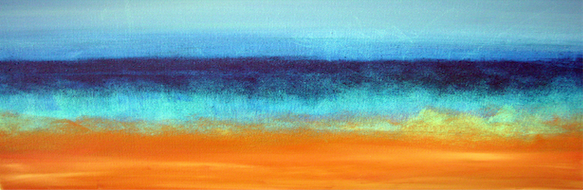コミュニケーションを劇的に変える5つのステップ
私たちの日常は、家族、友人、職場の同僚とのコミュニケーションで成り立っています。しかし、なぜか話が噛み合わない、意図が伝わらない、あるいは些細なことで感情的な対立が生まれてしまう、といった経験は誰にでもあるのではないでしょうか。その原因は、単なる「話し方」や「言葉選び」の問題だけではないかもしれません。
この記事では、コーチング理論に基づき、私たちのコミュニケーションを無意識のうちに支配している「心の仕組み」を5つのステップで解き明かしていきます。自分と相手の「心理的盲点」から、恐怖に基づく行動パターン、そして抵抗を生まない伝え方まで。これらのメカニズムを理解することで、人間関係におけるすれ違いの根本原因を突き止め、より円滑で豊かなコミュニケーションを築くための具体的な方法が見えてくるはずです。
1. なぜ「見えない」のか?:スコトーマとコンディショニング
コミュニケーションのすれ違いを理解するための最初のステップは、私たち一人ひとりが独自の世界を見ているという事実を認識することです。ここでは、この現象を「スコトーマ」と「コンディショニング」という2つの概念から説明します。
コンディショニング(条件付け)とは、認識や行動に影響を与える条件づけのことです。人間は、何かを認識する前に与えられた条件によって、何を認識するか、認識したものをどのように解釈するかが変化します。また、行動も、その前に与えられた条件によって影響を受けます。こうした条件づけによって、認識や行動の「フレーム(枠組み)」が固定化されます。そのため、私たちは一度「これはこういうものだ」という情報が入ると、そのフレームを通してしか物事を解釈できなくなります。
このコンディショニングがもたらす最大の問題は、条件づけられたフレームに合わない情報が認識できなくなる点です。私たちは客観的に物事を見ているつもりでも、実際には無意識のうちに情報を取捨選択し、自分のフレームに合わせて解釈しているのです。
そして、コンディショニングによって見えなくなっている情報や視点のことを、スコトーマ(心理的盲点)と呼びます。例えば、誰かに対して「この人はこういう人だ」というコンディショニング(決めつけ)があると、そのイメージに合わない相手の情報はスコトーマに隠れてしまい、認識できなくなります。その結果、「この人にこんなことができるはずがない」と過小評価して可能性を閉ざしてしまうことや、「この人は言わなくても分かっているはずだ」という思い込みで情報共有を怠り、後に「そんなこと聞いていない」というトラブルになるといったことが起こるのです。
これらのコンディショニングやスコトーマは、本人に自覚がないまま、物事を認識する際の「前提」として機能しているため、マインドの仕組みを知らなければ意識にあげること非常に困難です。
では、どうすればこの無意識の壁を乗り越えられるのでしょうか。その第一歩は、「自分にも相手にも、スコトーマやコンディショニングが存在する」という心の仕組みを認識し、日頃から意識に上げてみることです。そして、コミュニケーションの場で次のように自問自答してみるのです。
- 「今、相手との関係において、自分に見えていないこと(スコトーマ)は何だろう?」
- 「自分は相手に対して、どんな先入観(コンディショニング)を持っているだろうか?」
このように問いかけるだけで、無意識の癖に気づき、これまでとは違うコミュニケーションの選択肢が見えてくるはずです。同様に、相手の言動に対しても「相手はどんなフレームで物事を見ているのだろう?」「相手にとって、何がスコトーマになっているのだろう?」という視点で観察することで、なぜ話が伝わらないのかを理解し、より効果的な伝え方を工夫できるようになるでしょう。
2. なぜ「聞こえない」のか?:脳のフィルター「RAS」の仕組み
自分では伝えているつもりなのに、相手が話を聞いていなかったり、内容を全く覚えていなかったりするのはなぜでしょうか。その謎を解く鍵が、脳のフィルター機能であるRAS(Reticular Activating System/網様体賦活系)です。
私たちの脳は、五感を通じて絶えず膨大な情報を受け取っていますが、脳の処理能力の限界から、そのすべてを処理することはできません。そこでRASは、脳全体に張り巡らされたネットワークを使い、その時々で「重要なもの」だけを意識に上げ、それ以外をスコトーマにするというフィルターの役割を担っています。
では、RASは何を基準に「重要性」を判断しているのでしょうか。それは、以下の2つです。
- 価値(Value):自分にとって有益、関心がある、ゴール達成に必要だと判断される情報。
- 脅威(Threat):生命や安全を脅かす、恐怖を感じさせる情報。
コミュニケーションにおいて相手が上の空である時、それはあなたの話が、相手にとってこの「価値」と「脅威」のどちらにも当てはまらない情報としてRASにフィルタリングされ、スコトーマになっているのです。
この仕組みを知らずにいると、「なぜちゃんと話を聞かないんだ!」と思いストレスを感じてしまいます。しかし、「人それぞれRASの基準が違い、そもそも認識している世界が違う」という前提に立てば、コミュニケーションも変わってきます。
相手に確実に情報を届けたいのであれば、相手のRASを意図的に「開く」必要があります。広告などがよく使う手法は、「脅威」を刺激することです。例えば、「このままでは大変なことになる」といった恐怖を煽ることで、強制的に注意を引こうとします。しかし、日常の人間関係でこの方法を使うと、長期的には信頼関係を損なうため合理的ではありません。
したがって、私たちが目指すべきは「価値」に働きかけることです。相手が何に関心を持ち、何を重要だと感じているのかを推測し、伝えたい情報を相手の価値観と結びつけて話すことが極めて重要になります。相手がすでに重要性を持っている事柄にこちらの情報を関連づけることで、「これは自分に関係のある情報だ」と認識され、RASが開くのです。
また、自分自身のRASについても意識を向けることが大切です。過去の経験だけで形成された重要性で話を聞いていると、いつも同じような情報しか認識できません。しかし、未来の「ゴール」を明確に設定することで、そのゴール達成に必要な情報をRASが自動的に拾い始めるようになります。「この会話において、自分のゴール達成のために聞き逃している情報(スコトーマ)はないだろうか?」と自問することで、これまで見過ごしていた重要な情報に気づけるようになるのです。
3. なぜ「繰り返す」のか?:情動記憶が支配する意思決定
コミュニケーションにおける私たちの反応は、その場の論理的な判断だけで決まっているわけではありません。その背後には、無意識の領域に蓄えられた情動記憶、つまり強い感情を伴った過去の記憶が深く関わっています。
コーチングでは、私たちの思考プロセスは以下の4つのステップで進むと考えます。
- 知覚(Perception):五感を通じて外部からの情報を取り入れる。
- 照合(Association):取り入れた情報を、無意識にある過去の「情動記憶」と照らし合わせる。
- 評価(Evaluation):照合した結果、その情報が自分にとってポジティブかネガティブかを評価する。
- 判断(Judgment):評価に基づいて、どう行動するかの意思決定をする。
コミュニケーションで特に重要なのは、2番目と3番目のプロセスです。外から入ってきた情報は、それ自体に意味はなく、過去の情動記憶と結びつけられることで初めて「意味付け」と「評価」が行われます。例えば、ある人について、過去に楽しく関わった経験、つまりポジティブな情動記憶があれば、その人から「会いたい」という連絡がきた際に「会う」というポジティブな評価と判断に至ります。逆に、嫌な経験(ネガティブな情動記憶)があれば、「避ける」「先延ばしする」という判断を下すでしょう。
このプロセスは自動的に行われるため、客観的に情報を処理し、意識的に判断しているつもりでも、実際には過去の情動記憶に大きく左右された判断を繰り返していることになります。例えば、ある食べ物を過去に食べた時に美味しくなかったという経験がたった一度あっただけで、その食べ物全体を「嫌い」と評価してしまう場合があるように、たった一度のネガティブな経験が、その後の人間関係をずっと制限し続けている可能性があるのです。
この無意識のパターンから抜け出すにはどうすればよいのでしょうか。情動記憶そのものは無意識下にあるため、直接アクセスすることは困難です。しかし、「感情が動いた瞬間」に気づくことはできます。
誰かとの会話の中で、嬉しい、悲しい、腹が立つといった感情の動きを自覚した時がチャンスです。その瞬間に一度立ち止まり、「なぜ今、自分はそう感じたのだろう?」と内省します。そして最も重要なのは、その感情的な反応を、自分が実現したい「ゴール」の視点から再評価することです。
過去の経験から来る自動的な反応は、必ずしも未来のゴール達成に役立つとは限りません。「この感情のまま行動することが、本当に自分の望む未来や理想の関係性につながるだろうか?」と問い直すことで、過去のパターンを断ち切り、ゴールに基づいた新しい行動を選択できるようになります。
4. なぜ「怒る」のか?:恐怖が作る「制限ゾーン」の罠
過去の情動記憶、特に「恐怖」と強く結びついた記憶は、私たちの心の中に制限ゾーン(Restrictive Zone)と呼ばれる特殊な領域を作り出します。これは、私たちが慣れ親しんだ心理的な安全地帯である「コンフォートゾーン」と逆の関係にあり、制限ゾーンに踏み入ると強い不安や恐怖を引き起こして内側へ引き戻そうとする、いわば「檻」のようなものです。
この制限ゾーンは、幼少期の体験、例えば何かをしてひどく怒られたり、痛い目に遭ったりした経験を中心に形成されます。これらの経験から生み出された「こうしてはいけない」「こうしなければいけない」といった強固な信念(have to)が制限ゾーンを決めています。
この「have to」の信念の根底には、「~しなければならない。さもないとひどい目に遭う。(have to ~, or else ~.)」という恐怖が隠されています。そのため、「してはいけない」ことをしてしまったり、「しなければいけない」ことができなかったりすると、私たちはまるでパニックのような強い焦りや恐怖に襲われるのです。
例えば、「時間は1分たりとも遅れてはいけない」という恐怖と結びついた「have to」を持つ人は、少しでも遅れそうになるだけで、相手が許してくれる状況であってもパニックに陥ります。
この制限ゾーンの厄介な点は、自分自身を縛るだけでなく、他人がそのルールを破った時にも反応することです。それはまるで、「地雷を踏んだ」ような状態です。例えば、先ほどと同じ「時間は1分たりとも遅れてはいけない」という強い信念を持つ人にとって、待ち合わせ相手が数分遅刻してくることは、自分の制限ゾーンを侵害されたことを意味し、その反動として激しい怒りが湧き上がります。しかも、本人はその怒りが過去の恐怖体験に根ざした非合理的な反応であることに全く無自覚で、「相手が悪いのだから怒るのは当然だ」と思い込んでいます。
さらに深刻なのは、制限ゾーンを侵害されたと感じた時、私たちの無意識は「リベンジ(仕返し)」をしようと働くことです。このリベンジは、主に2つの形で現れます。
- 出し惜しみ:相手に対して協力しない、助けない、情報を与えないといった、受動的な攻撃。無自覚に本来の力を制限し、相手のパフォーマンスを妨げます。
- 制限ゾーンを刺激する:相手が嫌がることやイライラすることを、無自覚に行います。例えば、時間に厳しい相手に対してわざと遅刻するなど、相手の制限ゾーンを刺激するような行動を取ってしまうのです。
こうした無意識の行動は、特に行動を共にするチームや組織において、お互いの足を引っ張り合い、全体のパフォーマンスを著しく低下させる原因となります。
この罠から抜け出す鍵は、まず「自分や相手の強い感情的な反応の裏には、制限ゾーンが隠れているかもしれない」と認識することです。自分がカッとなったり、相手が不機嫌になったりした時に、「これは制限ゾーンの反応かな?」と抽象度を上げて観察する癖をつけることで、自動的な反応の連鎖を断ち切ることができます。
そして最終的には、ここでも「ゴールに立ち戻る」ことが重要です。「この『~すべきだ』『〜してはいけない』という恐怖に基づいた信念は、私たちが目指すゴールにとって本当に必要なのか?」と再評価するのです。ゴールから再評価できれば、恐怖にコントロールされることなく、不要な信念を手放し、「ゴールの実現のために、一緒に行動を修正していこう」という建設的なプロセスを進めていくことが可能になります。
5. なぜ「伝わらない」のか?:「プッシュ、プッシュバック」の法則
相手に良くなってほしい、チームのためにこうしてほしい。そうした善意から何かを伝えようとしても、かえって相手が意固地になり、反発されてしまった経験はないでしょうか。これは「プッシュ/プッシュバック」、つまり「押すと押し返される」という心の法則が働いているためです。
私たちが相手に「こうすべきだ」と強く働きかける(プッシュする)と、相手の心には無意識の抵抗(プッシュバック)が生まれます。これは、何かを無理に押し付けられると、バランスを取ろうとして押し返したくなる心身の自然な反応なのです。このプッシュは、前述した「~しなければならない。さもないと大変なことになる」という強制的な動機付け(have to)と密接に関連しています。
多くの人は、コミュニケーションがうまくいかない時に「もっと強く説得すれば相手は変わるはずだ」「しっかり伝えれば、相手もわかってくれるはずだ」と考えがちです。
しかし、プッシュバックが起こる本当の原因は、話の内容や伝え方の巧拙にあるのではありません。問題は、コミュニケーションのベクトルが一方的に相手に向いていることにあります。「言っていることは正しいと分かっているけど、そんな風に言われるとやりたくない」という感情は、まさにこの一方的なプッシュに対する反発なのです。
では、どうすればこのプッシュバックの罠を回避できるのでしょうか。答えは、逆向きのベクトル、つまり「聞くこと」から始めることです。相手に何かを伝える前に、まずは相手の世界を理解しようと努めるのです。
- 相手は現状についてどう思っているのか?
- どう感じているのか?
- なぜ、そのような行動を取っているのか?
このような点に関心を持ち、相手の話を聞こうとすることで、不思議なことが起こります。私たちは、相手に話を聞いてもらうと、自分も相手の話を聞こうとする性質があります。あなたが相手の話をまず聞くことで初めて、相手もあなたの話を聞く態勢が整うのです。
相手の言い分や事情を聞くプロセスそのものが、相手の不満や抵抗感を和らげ、プッシュバックが発生しにくい土壌を作ります。さらに、相手の話を聞く中で、こちらが伝えたい内容との共通点や、より抽象度の高い目的が見つかることもあります。そこから抽象度を上げて対話を進めれば、一方的な「説得」ではなく、双方にとって納得のいく解決策を「共創」していくことが可能になるのです。
何かを伝えたい時ほど、まずはこちらから相手へのベクトルを向けるのではなく、相手からのベクトルを引き出す。それが、ストレスのない風通しの良い関係性を築くための、最も効果的でパワフルな方法なのです。
まとめ:対話の質を高めるために
ここまで、コミュニケーションの裏に潜む5つの心の仕組みを見てきました。
- スコトーマとコンディショニング:私たちは皆、無意識の「色眼鏡」を通して世界を見ており、それによって多くの情報を見逃している。
- RAS:人の注意を引くには、相手の「価値」に響く形で情報を伝えなければならない。
- 情動記憶:私たちの判断は、過去の感情的な体験に大きく左右されており、意識的に「ゴール」から再評価する必要がある。
- 制限ゾーン:理不尽な怒りやパニックは、過去の恐怖が作った「情動記憶」が原因かもしれない。
- プッシュ/プッシュバック:一方的に押すと押し返される。まず「聞く」ことから始めなければ、相手の心は開かれない。
これらの知識は、単なるテクニックではありません。人間関係のあらゆる場面で起こるすれ違いや対立を、より高い視点から理解し、乗り越えるための「見取り図」です。
今日から、自分や相手の言動の裏にあるかもしれない心の仕組みに、少しだけ意識を向けてみてください。なぜ伝わらないのか、なぜ感情的になるのか。その根本原因が見えた時、あなたのコミュニケーションは、より深く、建設的で、豊かなものへと変わっていくはずです。
Liberty Coaching Radio
Liberty Coaching Radioは、リバティーコーチングの公式YouTube で配信中です。毎週、月曜日から金曜日まで1つのテーマに沿って、コーチング理論を活用した内容を配信しています。stand.fm と Spotify でも配信しています。
このブログ記事は、Liberty Coaching Radio vol.6~10 の内容に対応しています。
ブログと合わせて音声を聴くことで、理解がより深まります。
vol.6 コミュニケーションにおける盲点
https://youtu.be/2OLkpr4sH28?si=23A2sUKSw3vU1RXE
vol.7 効果的に伝える方法
https://youtu.be/nCYn_RiI3V4?si=woP6I1uE-aSxRAJC
vol.8 コミュニケーションにおける情動記憶の働き
https://youtu.be/Fav2czRE67w?si=8tdL7QAZdqyxLh0i
vol.9 人間関係の「制限ゾーン」
https://youtu.be/qF3wgFmxCt0?si=TPJ6_AUyixFmG1xe
vol.10 抵抗を生まない伝え方
https://youtu.be/7mIb14X9mws?si=9bL4mXfHQMqlYNFE